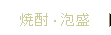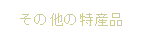|
 |
 |
| 其の十一、 くどき上手 亀の井酒造(株)訪問 2008年6月2日 |
 |
|
|
 |
 |

|
2008年6月02日(月)、長岡発07.53 とき301号に乗車。行く先は、山形県鶴岡市の亀の井酒造(株)である。鶴岡到着は10:27、2時間34分の道のりです。長岡→新潟間は上越新幹線 新潟→鶴岡間は在来線の特急「いなほ」です。
東京の飲食店さんと待ち合わせて訪問します。新潟駅から鶴岡駅までは、ほぼ日本海沿いに走ります。
 とりわけ村上市の海岸沿いの海は「笹川流れ」と呼ばれる景勝地で、とても綺麗な景観が続きます。佐渡との間にある「粟島」もすぐ近くに見えました。
とりわけ村上市の海岸沿いの海は「笹川流れ」と呼ばれる景勝地で、とても綺麗な景観が続きます。佐渡との間にある「粟島」もすぐ近くに見えました。
鶴岡駅に着くと、亀の井酒造(株)の今井社長に出迎えて頂きました。15分くらいで蔵に到着です。田園風景のなかにひときわ輝く「白壁の蔵」が見えます。
今回の訪問の理由に、東京の飲食店さんが開催する酒の会に「くどき上手を楽しむ会」を取り上げたことがあります。6月の第4週に新宿の地酒処、専門性の高い飲食店様での開催の詳細が確定しました。
さて、昨秋からの平成19BYの酒造りは終了していますので、今回の蔵見学は設備及び酒造りの概要の説明に留まりましたが、多くのサプライズを得ることができました。
1.今井社長は、30年ほど前から既に杜氏として酒造りをしています。今でこそ若い経営者が、自ら杜氏として酒を造ることは珍しくはありませんが、当時としては数少ない事例だったと思います。そのことが現在の成功に結びついているように、私には思われます。
1.蔵を案内していただいて一番思うのは、小さな規模の蔵ですが美味しい酒を造るために最善の設備が抜かりなく施されている。最新の技術を施した麹室、数多くのサーマルタンク、全館の冷蔵冷房設備、水の管理など、あらゆる部分が完璧のように思えます。
1.製造石数は1300石。仕込は基本的に1500kg仕込、半仕舞い、平均精米歩合47%〜48%。驚くことに蔵全体の平均精米歩合が大吟醸、純米大吟醸のそれです。使用米は、ほとんどすべてが酒造好適米、12種類の米を使って米による味わいの違いの楽しさを消費者に提案しています。
製品の大部分が、純米吟醸、純米大吟醸です。
そして、5月末に発売された「おしゅん」の説明を受けました。この商品は、山形県の指導を受けて商品化された、山形の地域特性にこだわったスパークリング吟醸です。
米は山形県産「出羽の里」、酵母も山形県産「チロソール高生産性酵母」を用いて仕込み、清澄された日本酒の中に炭酸ガスが入っています。口中ではじけるような清涼感のあるこれまでに無い日本酒です。更に、白のタイプと黒紫米の色素が抽出されたロゼのスパークリングワインのような赤のタイプがあります。おかげさまで今年の夏は、皆様より大変好評を頂いております。
 仕込蔵に続いて、出荷前の商品の管理をする白壁の蔵を案内されました。
仕込蔵に続いて、出荷前の商品の管理をする白壁の蔵を案内されました。
この蔵は、伝統的な白壁の土蔵をイメージして作られた建物です。1階部分は大型の冷蔵庫と空調設備で管理された作業場です。蔵から小売店まで途切れることなく温度管理がされています。
2階には、会議とかイベントに使われる広い空間があり、その背後に銅版ぶきの古風な茶室が設けられています。この茶室は、代々から伝わる母屋にあった茶室を移転したものだそうです。
欅(けやき)の木材といろんな彫り物がほどこされた欄間(らんま)、銅版で葺かれた屋根が昔の旧家らしく印象的です。
 更に、中三階には美術収集室があります。今井家の叔父さんにあたる著名な油絵画家「今井繁三郎」画伯の絵が飾ってあります。絵の名前は覚えていませんが、数点の雪をかぶった名峰「月山」の絵と抽象画です。
更に、中三階には美術収集室があります。今井家の叔父さんにあたる著名な油絵画家「今井繁三郎」画伯の絵が飾ってあります。絵の名前は覚えていませんが、数点の雪をかぶった名峰「月山」の絵と抽象画です。
この蔵の2階から外に目を移すと、6月でも正面に雪を頂く月山が見えます。まさに「今井繁三郎」画伯の描いた「月山」の絵のイメージと重なります。更に、出羽三山(月山、湯殿山、羽黒山)がパノラマのように美しく連なっています。
山々の麓からはなだらかに続くのどかな緑の田園風景と手前には羽黒山登り口の朱色の大鳥居が見えます。秋になると黄金色の稲穂が波打つ景色が一面に見えるそうです。大自然に囲まれたとても美しい風景の広がるキャンバスの中に蔵が位置しているようです。
この恵まれた「大自然」と「今井社長の人柄と強いチャレンジ精神」が美味しい酒を当然のように醸し出していることを理解する旅になりました。
|
|
|
|

 地酒サンマートについて
地酒サンマートについて
 お買い物について
お買い物について
 サイトマップ
サイトマップ
 買い物かご
買い物かご