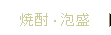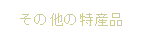|
 |
日本の酒造り方法はどの様な経緯を経て出来上がってきたのでしょうか。
元禄11年、江戸幕府の調査では当時、造り酒屋の戸数は27、251軒と記録が残っております。実際、造り酒屋は初めから純然たる産業資本をもって成立したものでもなければ、製造高の大きさを誇っていた訳でもなかったのです。
小造り酒屋は、一面では農村の副業的性格を持ち、他面地主的要素、即ち年貢米を利用しての造りをしていたとの指摘もございます。
ですから、副業的要素もあり、一軒当りの製成高は平均酒にしてわずか33石8斗となっております。今のメ−トル方に換算しますと、6、084リットルで一升瓶に直しますと3、380本になります。
その後、経済の発展と共に酒屋は財をなしたと言われております。
現在では産業資本の導入により灘(兵庫県)、伏見(京都)には46万石程の大手蔵も出来る様になりましたが、今でもなお、同族等による1、500〜1、600石以下の個人企業に近い造り酒屋が約75%も占めております。
最近の調査でも明治32年には14、731軒、第二次世界大戦敗戦直後の昭和20年には3、160軒に激減、その後昭和31年に至る約10年間で4、073軒まで増加しましたがそれからは減少の一途を辿り、平成6年10月現在においては2、320軒(実際製造している蔵元は1、890軒)と激減しております。
さて、酒屋はどんな方法で酒を造ったかと申しますと、「仕込み桶」と言って杉材を 組み合わせ作る木桶で、16世紀末期には十石桶が登場し、元禄年間には二十五石(4、500リットル)、三十石(5、400リットル)桶が使われておりました。
まず、酒米を搬入して米俵を開き、汗をぬぐいながら米を精米する搗き屋、搗き上がった精白米を桝で計る者、井戸水を汲み上げて流し場一杯に並んだ桶で米を洗う者、釜屋と言って大きな和釜で米を蒸す者、半地下の麹室で麹を造る者、もろみの仕込みやしぼりの製成作業する者等に分けられます。
これらの仕事を総括指導するのが杜氏(とうじ)という親方の役目で、工場制手工業方式とはこのような労働力の結集作業です。
こうした激しい真剣な労働は今日の労使間で見られる雇用契約では、得られるはずがありません。酒造りは誰でもすぐ受け持って責任ある仕事が出来るという者ではなく、長い経験とそれ相応の熟練が要求されるのです。
また、主従的温情的関係を維持していた事は昔、封建的温情的束縛を強いられていた農漁民の忍耐制と服従制に負う者と考えられます。
この様に、工場制手工業方式を利用して作業能率の向上を図った事と、農漁村の季節労働者を」使った事などで元禄期以前2回の株改め(酒屋株)で千石の生産規模を持つ造り酒屋がますます隆盛に向かう様になったそうです。
|
 |
|
<< 戻る 目次 次へ >>
|
|
|

 地酒サンマートについて
地酒サンマートについて
 お買い物について
お買い物について
 サイトマップ
サイトマップ
 買い物かご
買い物かご